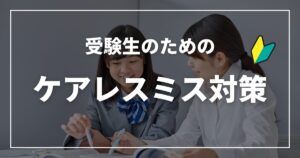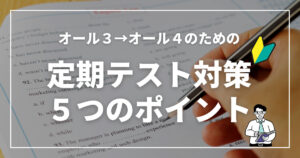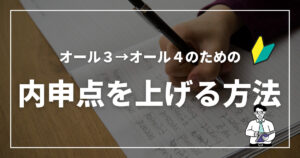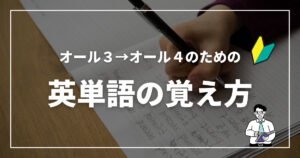点数を見るだけで終わらせない!成績を変えるテスト後の行動とは
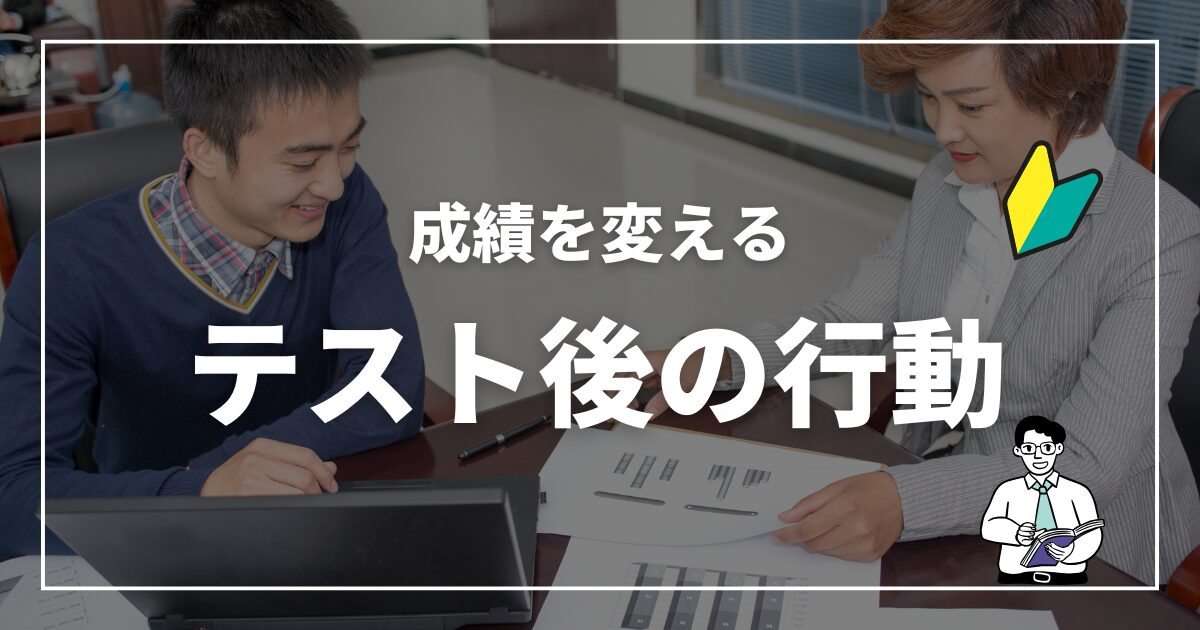
こんにちは、個別進学塾トークス平塚校の宮崎です!
成績アップにおいて、テストの点数を追いかけることはたしかに大事なんですが、テストの点数自体はあくまでも「結果」にすぎません。
良くても悪くても結果をどう受け止め、どのような行動に移すかという「視点の差」こそが、以降の成績に大きな差を生むんじゃないかと僕は考えています。
これまで何百人もの生徒と向き合ってきましたが、着実に成績を伸ばしていく生徒には一つの共通点があります。
それは、テスト後の振り返りを徹底していること。
振り返りとは、ただ間違いを直すだけではなく、
・なぜ間違えたのか
・何が足りなかったのか
・次にどうすればいいのか
こういった原因を自分の言葉で整理することを指します。
テストが終わった直後は、「よかった」「悪かった」という表面的な判断で終わってしまいがちですが、ここに大きな学びのチャンスが隠されています。
本日は、「テスト後の振り返り」がなぜ成績向上のカギとなるのか、掘り下げていきます。
この記事を読み終える頃には、「テスト後」に対する見方が、きっと大きく変わっているはずです。
いや…変わってくれ!!

個別進学塾トークス代表の宮崎です!
大手塾に勤務後、独立し茅ヶ崎市に自分の塾を開校。常に満席になることが増えたため、2教室目として平塚市に個別進学塾トークスを立ち上げました。
10年以上の指導歴があり、数百名の合格者を出している、神奈川県の高校受験・大学受験の専門家です。
この記事の他にも、茅ヶ崎市・平塚市の中学生・高校生・保護者のみなさんに向けた記事を書いているので、よければこちらからご覧ください。
成績向上のための大切な視点
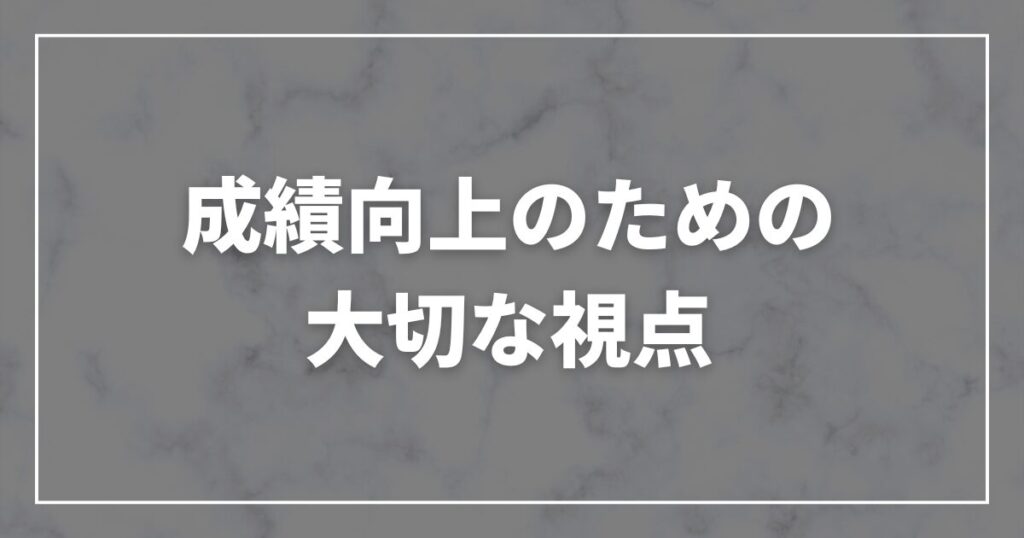
成績を伸ばすためには、「テストは終わってからが本番」という意識を持つことが大事です。
テストの点数そのものよりも、その後にどう行動するかが次のテストの点数に大きく関わってくるからです。
テストの結果とは学力の一部を示すに過ぎず、そこから
・何を学ぶか
・どこを直すか
という視点を持たなければ、ただ単に点数を受け取るだけで終わってしまいます。
テストの内容を振り返らなければ、同じ間違いを繰り返し、成長のチャンスを失ってしまうんですよね。
実際に教室であった例を挙げると、数学のテストで平均点以下だった中学2年生の男の子が在籍していたんですが、彼は最初「今回は難しかった」で終わらせようとしていました。
担当の先生と一緒に点数の原因を探ると「問題文の条件を読み飛ばしていた」「公式の使い方を暗記に頼っていた」ことがわかりました。
そこから、「設問を丁寧に読む訓練」「なぜその公式が使えるかの理解」を目標にし、学校や塾の勉強を見直したことで次のテストで15点アップしました。
このケースのように、テスト後に自分の勉強法そのものを見直すことが、成績向上に直結します。
かくいう僕自身も、仕事や家庭の中でこの「振り返り」という行為を最も重視しています。
失敗や成功にかかわらず、結果をもとに行動を変えなければ、同じ結果が繰り返されるだけだと実感しているからです。
だからこそ、子どもたちにも「テストの後に何をするか」が最も重要なのだと、常に伝えるようにしています。
「テスト後の行動こそが未来を変える」という意識があることで、テストは終わりではなく、次のステップへのスタートになるでしょう。
具体的な振り返りのポイント
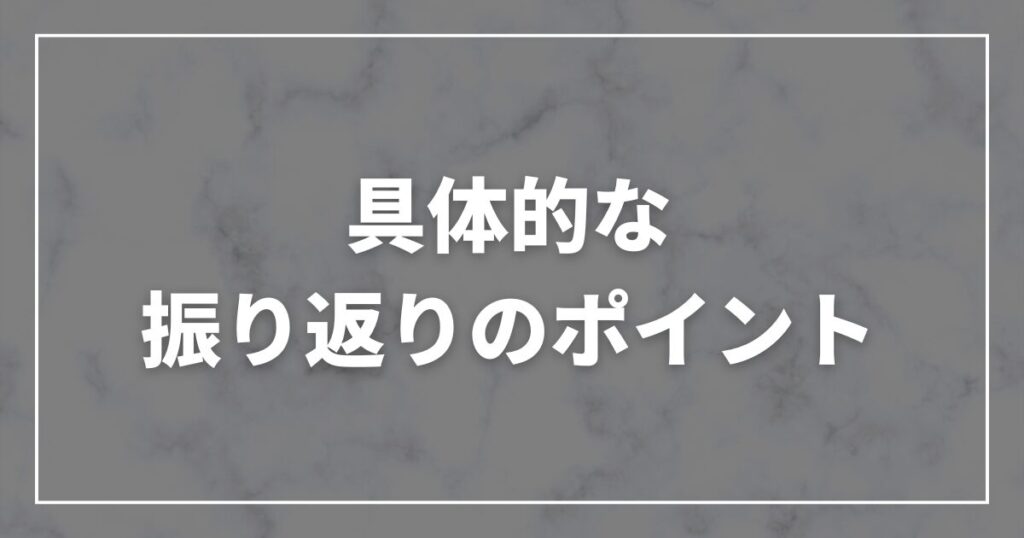
さて、それでは具体的に何をすればいいのか。
テスト後に行うべき振り返りの中心は、
・間違いの原因分析
・次に向けた具体策の明文化
です。
「一生懸命にがんばります」といった漠然とした反省では、次につながる改善は生まれません。
テストでのミスには必ず原因があり、それが分からないままだと次のテストでも同じパターンで点を落としてしまうからです。
反省と対策を切り離して考えるのではなく、原因を見つけ、その場で行動計画に落とし込むことが必要です。それが、「次こそはできるようになる」実感につながります。
具体的な方法としては、
①「正解した問題」「わかってたけど不正解だった問題」「不正解だった問題」へと、すべて振り分ける
・「不正解だった問題」のうち説明を聞いてもわからない問題は無視する
②間違えた原因を1問ずつ記録する
・「用語の意味を曖昧に覚えていた」「問題文の条件を読み違えた」「計算は合っていたが設問の形式を間違えた」など、細かいレベルで分類する
③原因ごとに「どんな復習を、いつ、どれぐらいやるか」を具体的に書き出す
・振り返りノートを作成したり、チェックリストの形式にすると定着しやすい
このようなアクションを取るとよいでしょう。
テストが終わってから時間が経つと熱量が下がってしまうので、できればテスト用紙が返却された直後に実施できるといいですね。
ちなみに僕たちの塾では、テスト後に必ず自分の「冒険の書(勉強計画表)」を使い、点数よりも原因に着目するよう指導しています。
過去には、毎回の振り返りでいわゆる「凡ミス」「知識の乱雑さ」を徹底的に洗い出し、そのための予防策を身につけた生徒が、たった3ヶ月で理科の点数を40点ほど上げたこともあります。
これは僕の経験則になりますが「なぜ間違えたか」「どうすれば次はできるか」を習慣として考えられる生徒は、例外なく伸びますね。
「原因を掘り下げること」と「行動につなげること」を行いましょう。
振り返りの心理的効果
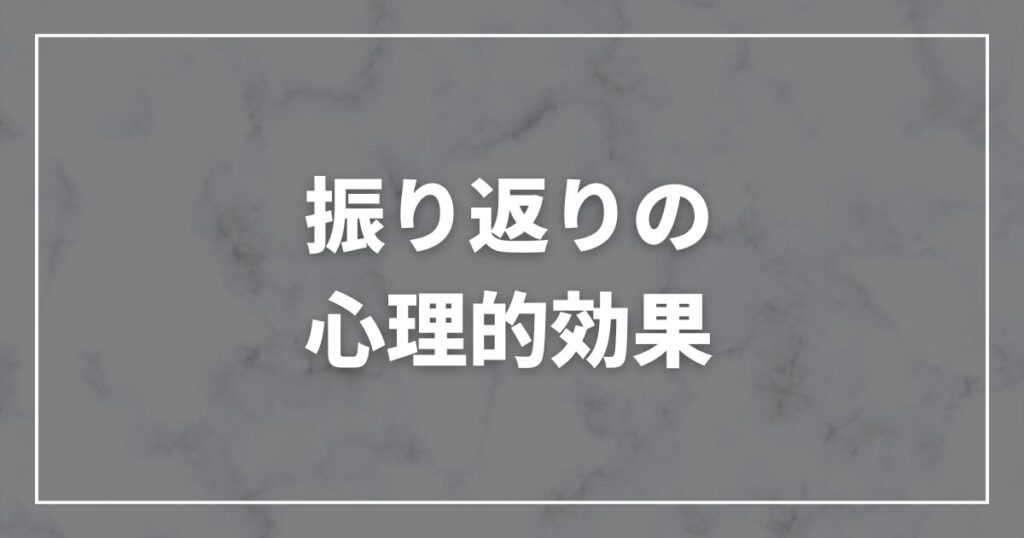
話の本筋からは少し逸れますが、振り返りには学力面だけでなく、心理的な安心感や自信を育てる効果もあります。
実はこれ、継続的に努力できる精神力を作るうえで、とても大きな意味を持つと感じています。
それは自分の行動を振り返ることで
・やるべきことが明確になる
・次はこうすればいいと分かる
といった整理された状態が得られ、不安や焦りを軽減できるから。
テストの結果に一喜一憂するだけでは自分を見失いやすくなりますが、振り返りを通して「原因と次の手」が分かれば、「これを克服すれば、成長できそう…」といった未来が見えます。
ある生徒が社会のテストで思うように点が取れず落ち込んでいたとき、「どこで点を落としたのか」「どんな対策が考えられるか」を一緒に整理したことがあるんですよね。
すると、
「覚えたと思ったけど覚えてなかった」
「一問一答だけでは記述に対応できなかった」
といった原因が明確になったことで、
「次に向けてやることが分かった」
と表情が変わり、結果として、不安よりも「やればなんとかなる」という感情の方が大きくなり、再び机に向かうようになった…というエピソードがあります。
この前向きな感情ってけっこう強くて、今までなかなか勉強に集中できなくて成果も残せなかった…という生徒がいきなりゴリゴリに勉強するようになったりするんですよ。
それぐらい、(なんとなくでも)未来が見えるパワーって大きいんだなと僕は思っています。
実際に僕たちの塾でも振り返りの時間(当塾では「作戦会議」という、1on1の生徒個人面談があります)はとても大切にしているんですけど、それは学力面・心理面の両面を強くして効率的に成績アップにつなげよう、という意図があります。
そんなわけで、振り返りには学力だけでなく「次はやれる!」という心の余裕を作る力があるのではないかと。長期的に努力を続けるためには、かなり価値のある効果だと言えるでしょう。