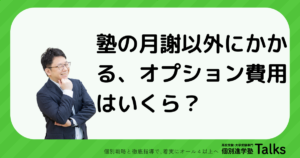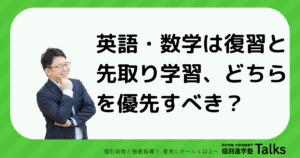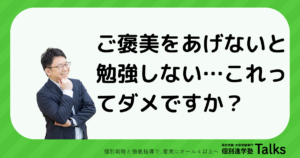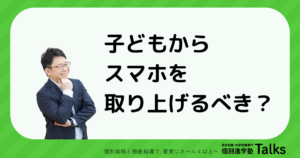【質問きてた】子どもが危機感を持たない…悔しがらないのはなぜ?
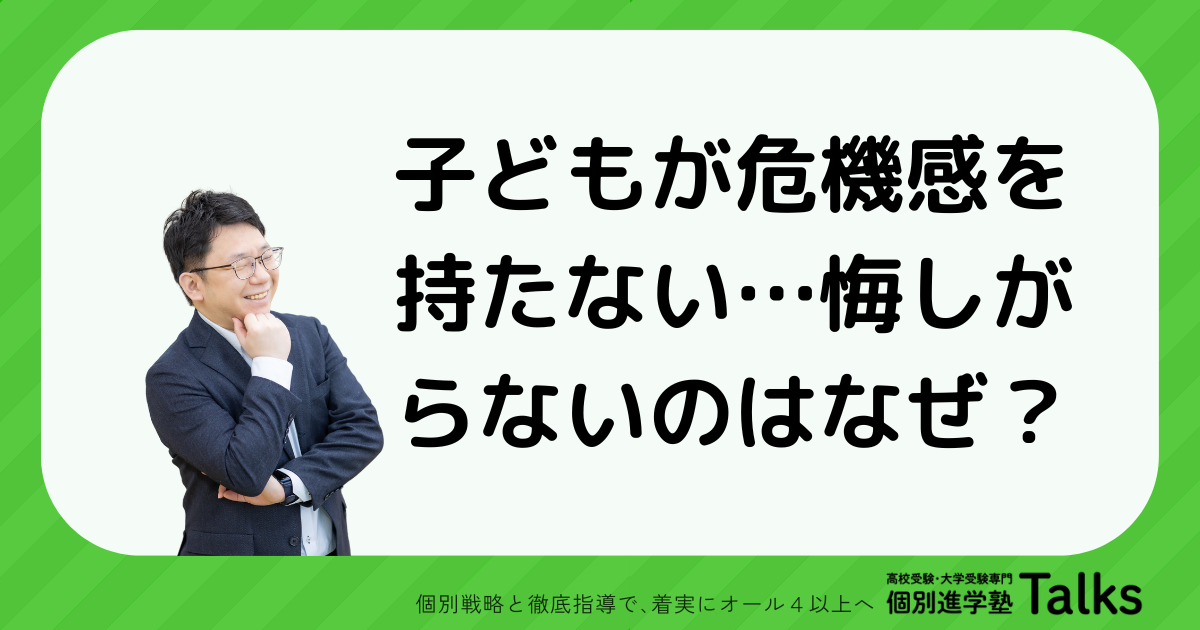
こんにちは、個別進学塾トークス平塚校 代表の宮崎です。
先日、とあるお母さんとの個別面談で、
うちの息子なんですけど、テストでイマイチな点数を取ってきても、あんまり危機感を持たないようで…。
先生からもキツく言ってもらえませんか?
というご相談をいただいたので、せっかくですから宮崎の見解を述べてみます。
こちらの相談にもある通り、テストの点数が思わしくなくても、まるで気にする様子もなく過ごす子どもに対して、戸惑いや不安を感じたことがあるお母さんってそこそこいるんじゃないかなと。
親の立場として
・なぜ悔しがらないのだろう?
・このままで大丈夫なの?
と心配になるのは当然ですが、実はその無反応の裏には、どうせ頑張っても意味がないという静かな諦めが隠れていたりします。
こうした子どもたちに必要なのは、結果に対する叱咤ではなく、できるかもしれないと感じられるような肯定的な関わり方です。
なぜ子どもが悔しがらなくなるのか、その背景にある心の動きと、親ができる声かけの工夫について、具体例を交えて詳しくお伝えしてまいります。

個別進学塾トークス代表の宮崎です!
大手塾に勤務後、独立し茅ヶ崎市に自分の塾を開校。常に満席になることが増えたため、2教室目として平塚市に個別進学塾トークスを立ち上げました。
10年以上の指導歴があり、数百名の合格者を出している、神奈川県の高校受験・大学受験の専門家です。
「悔しがらない子ども」に戸惑う親が増えている
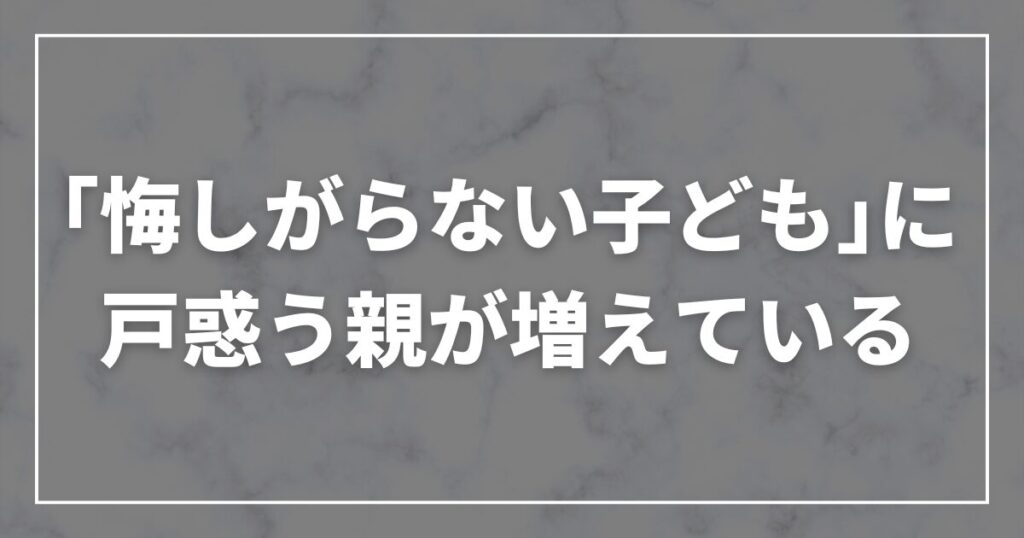
あらためて、宮崎はこの個別進学塾トークスも含め塾長として10年以上現場に立っていますが、
・もっと悔しがるべきでは?
・危機感を持ってくれたら…
と不安になるお母さんの声をよく耳にします。
学校のテストで思うような点が取れなかったにもかかわらず、悔しがる様子を全く見せない子ども。
たしかに、親としては心配になるのも当然です。
「少しぐらい悔しがってくれれば…」「このままでいいと思っているの?」と願う気持ちは、どのご家庭でもきっと一度は感じたことがあるでしょう。
ただ、少し立ち止まって考えてください。
たしかに子どもの成績は気になると思いますが、ただ単に悔しがらない様子を見るだけで、「やる気がない」「努力をしようとしない」と判断するのは早計です。
もう5年ぐらい前の話になりますが、数学のテストで40点台を取り続けている中学2年生の男の子が入塾してきたことがあります。
彼は40点台という結果にもかかわらず、平然と「どうせ俺、数学苦手だし」と言い放っていました。
お母さんは「何を考えているのか分からない」と嘆いていましたが、詳しく話を聞いてみると、小学校の頃から何度も算数でつまずき、
そのたびに「もっと頑張りなさい」「ちゃんとやりなさい」と言われてきたそうです。
自分なりには頑張ってるつもり。けれども点数がぜんぜん伸びない。。
そうした経験が積み重なり、やがて「どうせ頑張っても意味がない」という思考に行き着いてしまったとのこと。
なるほど、無関心に見える態度の奥には、頑張る理由が見つからないという静かな諦めが潜んでいることがわかりますね。
自分なりに努力したにもかかわらず、成果が出なかった経験を繰り返していると、
・どうせやっても無駄だ
・意味ないことはやりたくない
・無駄なことをしなきゃいけない意味がわからない
と感じるようになり、次第に感情を表に出さなくなっていきます。(大人も同じですね。)
頑張れないのではなく、頑張っても意味がないと思っている
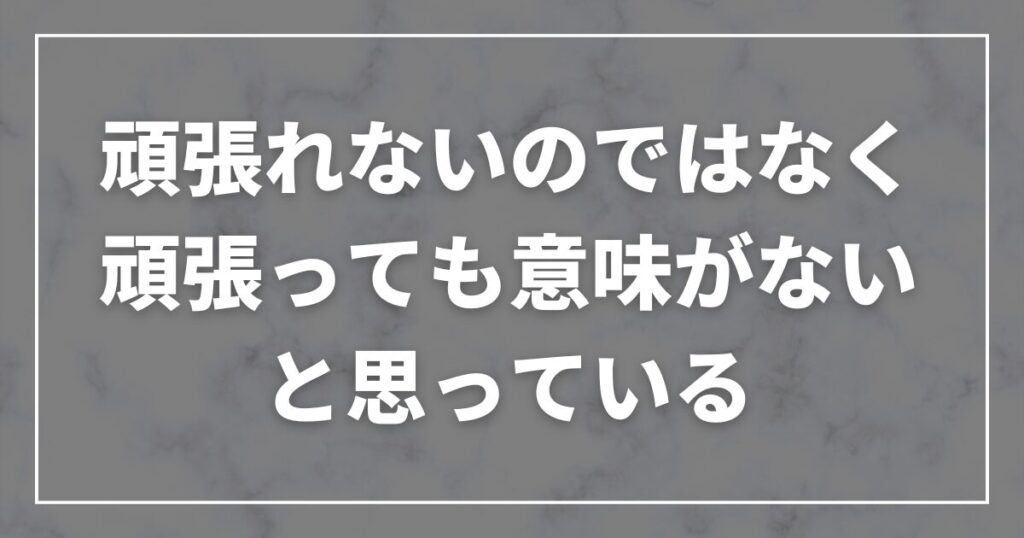
さて、多くのお母さんたちは「なぜうちの子は頑張れないのか」と悩みますが、その問いには少し違った視点が必要です。
実際のところ、そのような子どもたちは
「頑張れない」のではなく、
「頑張っても結果につながらない」と信じてしまっている
状態になっている子が多いです。(昭和世代からすると、いやお前何言ってるんだ!と感じなくもありませんが、、)
そう、これまで努力しても報われた実感が得られなかった子どもにとって、「また失敗するかもしれない」という不安はとても重たいものです。
このような思い込みは、成功体験の不足や、周囲との比較によって形成されていきます。
特に思春期以降の子どもは、自分の立ち位置を同年代の仲間と比べて確認しようとする傾向が強くなりますからね。
成功体験の不足、周囲との比較を繰り返す中で
・自分は劣っている
・あの子はできるけど自分は無理だ
・自分にはそもそも能力がない
と感じてしまった瞬間に、挑戦すること自体への意欲が一気になくなってしまいます。
中には、最初から手をつけることすら諦めてしまう子も一定数いるでしょう。
このように、やる気なく見える態度の裏には、何度も折れた心が隠れている場合があります。
そんなときに、表面的な態度だけを見て「頑張りなさい」「危機感を持ちなさい」と言ってしまうと、心の扉はさらに閉じてしまいます。
「どうせやっても無駄」
という価値観の完成ですね。
仮にこの状態で無理やり勉強をさせても、ごまかしたり、答えを写したり、ただやってるだけになってしまい、
・長時間勉強してるのに、ぜんぜん成果につながらん!
・やっぱり、努力したって意味ないんだ!
という悪循環にハマります。
正直、こうなってからの脱却はけっこう大変ですよ。いや、マジで。
この悪循環に突入する前に、なんとか手を打ちたいところですね。
プロセス重視の声かけで、自己効力感を育てる
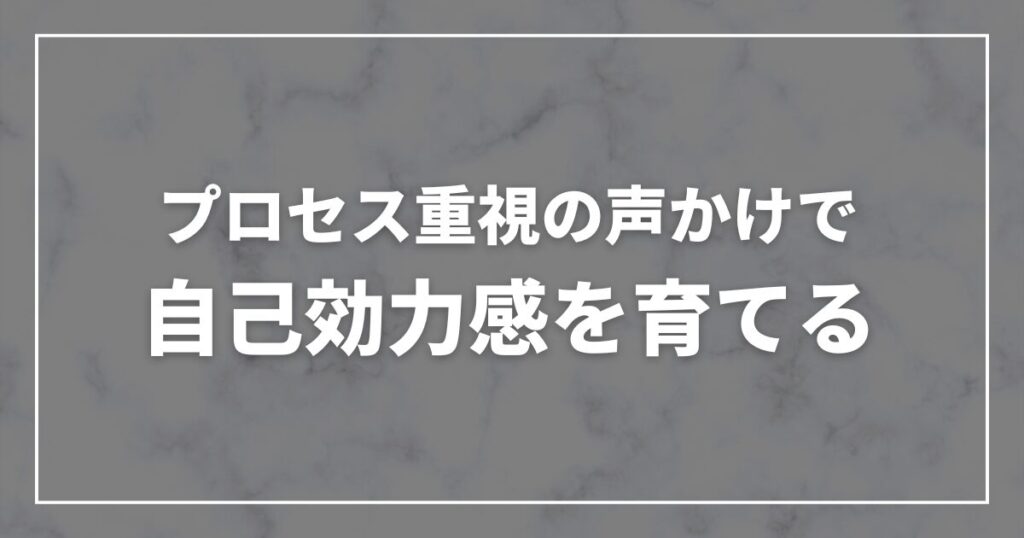
子どもが「どうせやっても意味がない」と感じている場合、その意識を変えるためには、自己効力感を育てるアプローチが欠かせないと考えています。
自己効力感とは、目標を達成する際に自分ならできる!きっと上手くいく!と信じられる自己認知のことです。
似た言葉に「自己肯定感」がありますが、こちらは無条件に「自分には価値がある」と認めることができる感情を指します。
どちらも「自信」に関係しますが、
・自己効力感は「できそう!」という行動の自信
・自己肯定感は「できなくても自分には価値がある!」と思える心の土台
というイメージを持っていただけたら。
この自己効力感が少しでも芽生えれば、行動に向かうエネルギーが自然と生まれてきます。
では、どうすればその芽を育てられるのか。それは、
結果ではなく“過程”に目を向けて声をかけること
です。僕はこれが最強の解決方法だと思っています。
事実、僕も含めた個別進学塾トークスの講師全員、この考え方で生徒のみなさんに接しています。
実際に教室で「この前より机に向かう時間が長かったね」「問題文をよく読んでいたね」といった、小さな変化を具体的に伝えると、生徒たちは「自分の頑張りを見てくれている」と実感してくれるんですよね。
以下のインタビュー動画でも、生徒自身が語ってます。
これ、本当に大人もそうだと思うんですけど、点数(結果)だけで評価され続けると、「できた・できない」だけで自分を測ってしまいがちで、、
上手くいっているときは問題ないんですけど、上手くいかなかったときにパフォーマンスが著しく下がります
そうではなく、努力のプロセスに目を向ける。
すると、自分の中に小さな成功体験が積み重なり、やがて「次はもう少しやってみよう」という前向きな気持ちへとつながります。
「できるようになった」瞬間よりも、
「できるようになろうとしている」姿勢に注目する
ことで、挑戦すること自体が肯定される環境が生まれます。
もし失敗したとしても、その取り組みを肯定する声かけがあれば、子どもの中に「やってみてよかった」という感覚が残って、それが自己効力感の土台になるんじゃないかなと僕は考えています。
一番認めてほしいお母さんお父さんという存在から信頼され、努力の過程に価値があると認められた経験は、子どもにとってかけがえのない支えになります。
ぜひ、結果ではなく“過程(プロセス)”に目を向けて声をかけてあげてください。
本日もご覧いただき、ありがとうございました!
こちらに勉強・受験に役立つ記事などをまとめました◎
●神奈川県の公立高校紹介

●神奈川県入試のしくみ

●文字数42,000文字以上の
『成績アップの教科書』配布中!

●個別進学塾トークスの受講生実績

●個別相談・体験授業はこちらから!

成績アップと志望校合格を目指すなら、高校受験・大学受験に強い、平塚市・茅ヶ崎市の進学型個別指導塾トークスへぜひ一度ご相談ください。
これからも個別進学塾トークス平塚校では、平塚市、茅ヶ崎市、藤沢市、大磯町に住んでいる小学生・中学生・高校生の勉強や受験について、役に立つことをお伝えしてまいりますね!