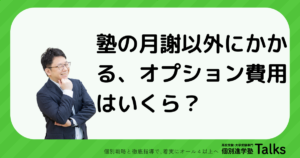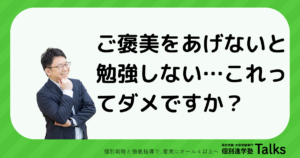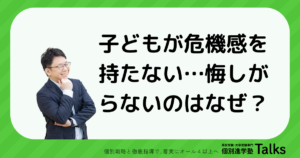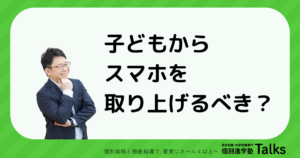【質問きてた】英語・数学は復習と先取り学習、どちらを優先すべき?
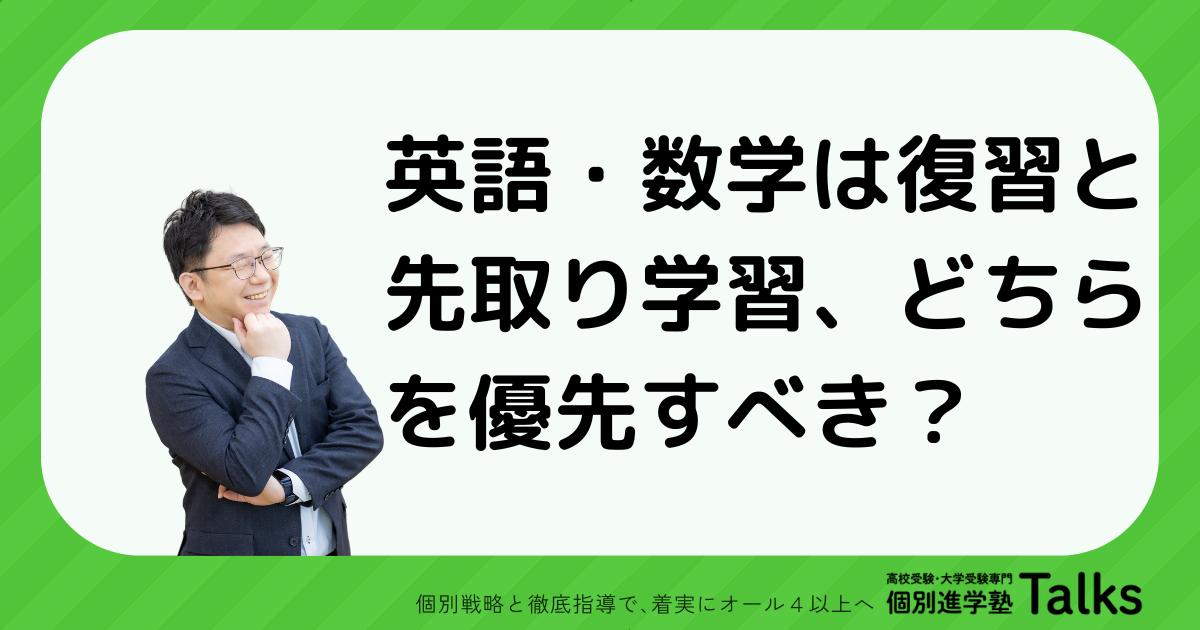
こんにちは、個別進学塾トークス平塚校 代表の宮崎です。
先日、中学2年生の息子を持つお母さんからこんな相談がありました。
息子は英語・数学が苦手で先取り学習をさせたいと思い、塾に相談しました。すると「基礎が固まっていないと先取り学習をしても効果が出ない」と言われ、1年生の内容を復習する指導を提案されました。息子の成績は平均より少し下くらい。私としても焦りを感じているのですが、このまま塾の方針に従うべきでしょうか?
僕も長年塾講師をやっておりますが、英語や数学を苦手とする子は思ったより多いです。
英語や数学が苦手となってしまう原因は、挙げればキリがありません。
質問いただいたお母さんと同じように、「もしかしたら先取り学習をさせれば、余裕を持って授業に臨めるのではないか?」と考える方も少なくないでしょう。
しかし、僕は断言します。
英語や数学の安易な先取り学習は、おすすめしません。
それは、英語と数学という科目は積み重ねの科目であるからです。
今回は英語・数学の科目としての特徴と、先取り学習の効果的な使い方を中心に、詳しくご紹介します。

個別進学塾トークス代表の宮崎です!
大手塾に勤務後、独立し茅ヶ崎市に自分の塾を開校。常に満席になることが増えたため、2教室目として平塚市に個別進学塾トークスを立ち上げました。
10年以上の指導歴があり、数百名の合格者を出している、神奈川県の高校受験・大学受験の専門家です。
英語や数学は、積み上げるピラミッド型の科目
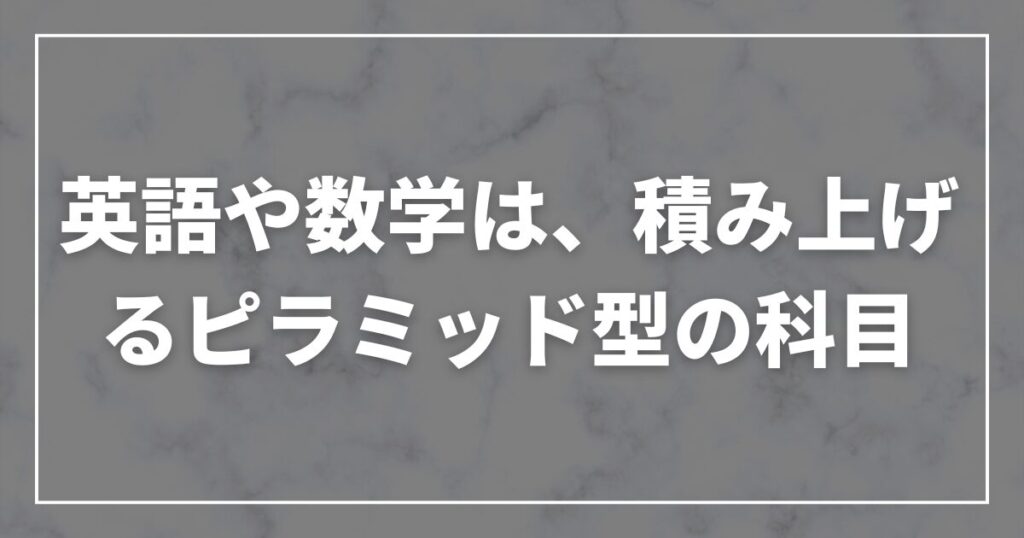
英語と数学は、前に習った内容を基礎として次の単元へ進む、いわばピラミッドのような構造です。
この2科目が厄介な理由は、ほとんどここに集約されます。
英語についてお伝えすると、
高校受験や大学受験では長文読解が必要となるため、英語長文の読解がピラミッドの頂点(受験英語におけるゴール)となります。
そして、長文を読むためにはまず、短い文を1文ずつ正確に読めなくてはいけません。
このとき、英文法をある程度理解していなければ、正確に読解することは難しいでしょう。
時制(過去・現在・未来)や対象の関係性(人・もの)を正しく把握できないと、短い文とはいえ誤って読み解いてしまいますからね。
たとえば、
The girl who is playing the piano over there is my sister.
という英文があり、この文章の動詞を探すときに
「 is playing」が動詞だ!!
と判断してしまうと、100%不正解です。
正解は、
The girl ( who is playing the piano over there ) is my sister.
こちらの通り、my sisterの前の「is」がこの文章の動詞です。
これは中学3年生で習う関係代名詞という文法を使った文で、文全体は
「あそこでピアノを弾いている女の子は、私の妹です。」
という日本語訳になります。
手順でいえば、
① 関係代名詞のカタマリ(who から there まで)を訳す。→「あそこでピアノを弾いている」
② それが説明している名詞(先行詞)を訳す。→「女の子は」
③ 文の残りの部分(述語)を訳す。→「私の妹です」
このような手順が必要です。
実際の入試や定期テストでも、このような英語長文の和訳問題は頻繁に出題されます。
上記の例では関係代名詞でしたが、中学1年生の段階でも
三単現のs、複数形のs、助動詞can、過去形、進行形、to不定詞
といった文法たちが立ちふさがります。
もっと言えば、文法事項の勉強をするためには、アルファベットの読み書きはもちろん、基本的な英単語を覚えていなくてはなりません。
小学生や中学1年生の内容が、高校・大学受験における英語長文まで、ピラミッド形式でつながっているんですよね。
つまり、もしも英語が不得意なら、先取り学習を行うのではなく復習を優先させたほうが効率いいと考えます。
これは数学でも同じで、英語・数学ともに
・単元の内容が基礎から順に積み上がっていないと理解が難しい
・学校の授業を1回聞いただけでは定着が難しい場合がある
という特性があるため、学年が上がるごとに苦手意識を持つ子が多くなる傾向があります。
今まで教わった内容や前学年の復習をしっかり行い、土台を固めたうえで丈夫なピラミッドをつくれるように行動しましょう。
既習内容の復習だけでは限界がある
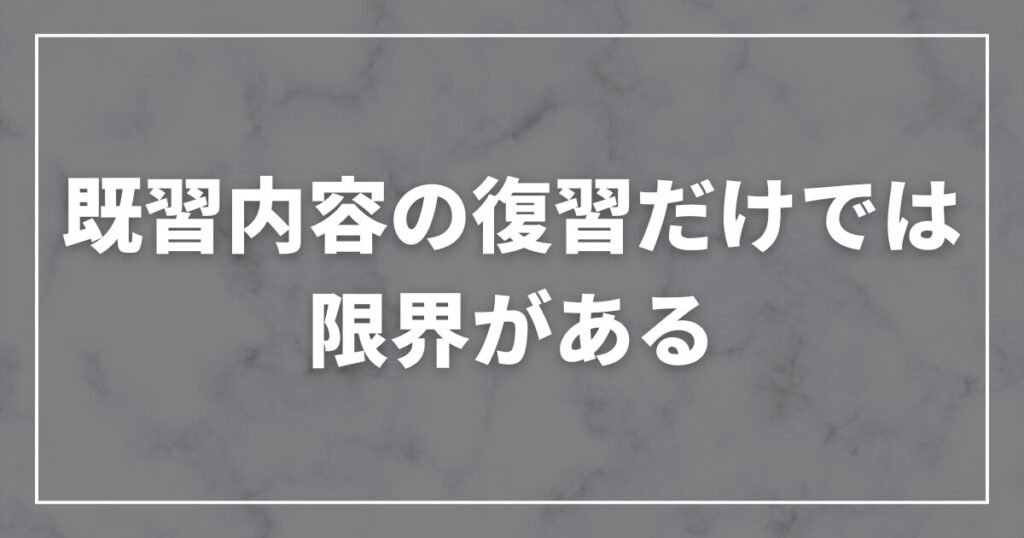
それでは、先取り学習は全く意味がないのでしょうか。
ここまで基礎固めの重要性をお伝えしてきましたが、実は復習するだけでは成績が上がらない場合もあります。
たとえば、
・現在の単元をしっかり理解している(人に説明できる)
・成績上位をキープしている
・学校の授業内容、スピードでは物足りない
といった場合だと、既習の内容を復習する必要はあまりなく、むしろその時間を先取り学習に充てたほうが効率がいいですね。
単純に考えて次の単元を予習してから学校の授業に臨むほうが、既に内容理解が進んでいるため、習熟度合いが上がるはずです。(まぁ、テキトーに予習していてもあまり意味はないんですけどね…)
本人の目標にもよりますが、勉強においては基本的に周りのペースと同じままでは、周囲と差がつきません。
ゆえに中堅〜上位のポジションを目指すなら、絶対にどこかのタイミングで復習中心→先取り中心の勉強に切り替える必要があります。
既習内容の復習や基礎固めももちろん大切ではありますが、それだけでは応用問題の正答率が上がらないからです。
応用問題で得点するには、基礎知識に加えて類題演習の経験値が必要ですから、難易度の高い問題の演習を行わないといけません。
基礎固めを先取り学習&学校の授業で完了させつつ、その後の自宅学習で発展的な問題と格闘できると理想的ですね。
「わかったつもり」が一番こわい
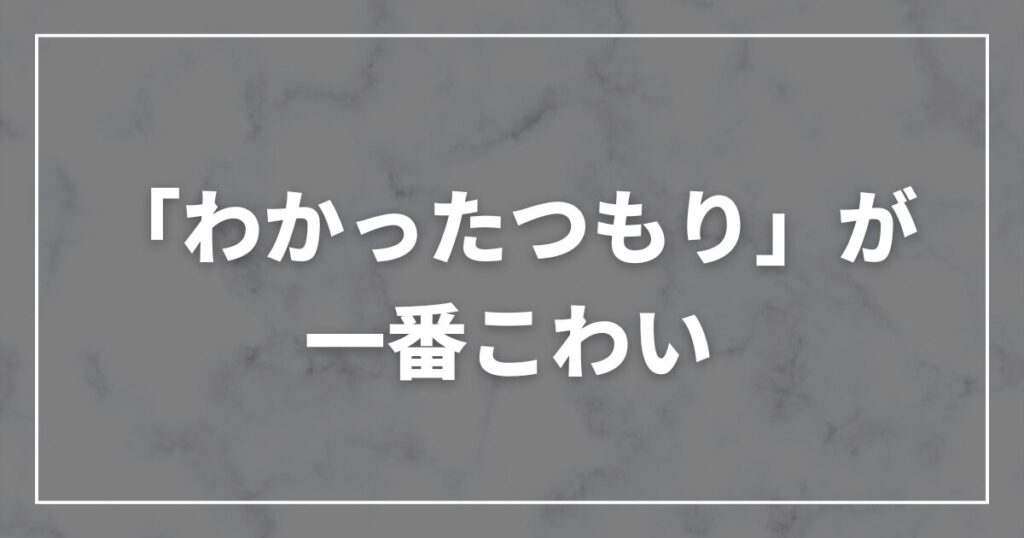
学校の授業は基本的に、
これまでに習った内容は、全員が理解している
という前提で進んでいきます。
そのため、話の前段階が理解できていないと、自分が分からない話を延々と聞かされている状態となり、ただ時間が過ぎるのを待つことになってしまいます。
そして、最も避けたいのが、
・こんなこと、今さら質問するのは恥ずかしい…
・質問するのも面倒だし…
という気持ちが生まれてしまうこと。
わからないことをさらに積み重ねてしまい、気づけば大きな遅れとなってしまいます。
もっと言えば、わからないことに気づいていない、わかったつもりになっていることが一番こわいです。
内容を理解したか否かを判断するには、
「なぜ、その答えになるのか?」を、自分の言葉で説明させる
方法がおすすめです。
「なんとなく」「雰囲気で」解けている問題は、残念ながら本当に理解したとは言えません。
たとえば、国語の選択問題。
正解の選択肢を選べたとしても、「なぜ他の選択肢は間違いで、これが正解だと言えるの?」と質問したときに、「なんとなく、これが一番しっくりきたから」と返ってきたら、それは理解できていません。
大切なのは、「本文のこの部分にこう書かれているから、この選択肢が正解だ」と、明確な根拠を本文中から探し出して説明できること。
感覚で解いているうちは、少し文章が複雑になったり、設問の意図が掴みにくくなったりすると、すぐに太刀打ちできなくなってしまいます。
この「説明できる」というアウトプットができて初めて、その単元を理解したといえるでしょう。
盤石な基礎という土台があってこそ、先取り学習は強力な武器になります。
「わかったつもり」を防いだ上で、既習範囲の復習と先取り学習、状況に合わせて取り入れるといいかもしれませんね。